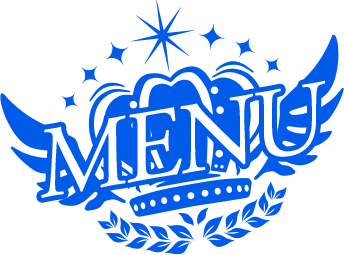ここは私立凰守学園。
生徒の個性を尊重し、「友愛・好奇心・探求」の3つを教育理念としたそこそこの歴史と伝統のある学園だ。学業はもちろん、様々な部活動を通して、生徒たちは日々健全な精神と肉体の育成に励んでいる。
今年も彼らが心待ちにしている文化祭の季節がやってきた。
クラスの出し物や、部活動ごとの成果発表の準備で賑わっている生徒たちを尻目に、明らかに浮かない表情でうつむき加減の四人がいた。
「軽音楽部」の3年生たちだ。
無理もない。彼らは凰学“最後”の軽音楽部員になろうとしているのだ。
彼らを“センパイ”という後輩は一人もいない。かつては一学年で何バンドも組めるだけの部員がいたこともあったが、今や彼ら四人が組む1バンドを残すのみなのだ。
軽音楽部の衰退に目をつけた生徒会は、その強権的な当代の生徒会長を筆頭に、1年をかけて、軽音楽部廃部の筋道を確固たるものにした。卒業式を間近に開かれる凰学の文化祭は、廃部への最後の花道としては格好の舞台となってしまった。
年も間も無く変わろうかというある日の放課後。ギターを抱え重い足取りで帰路につくケンスケはいつもよりも早く河川敷に差し掛かった。気分が乗らず、珍しく部活をサボってしまったからだ。
――歌声が聞こえてくる。
……。ただの歌声じゃない!とんでもなく上手い。それになんだ、力強くて凛としていて…。
誰だ!?合唱部でもこんな声してる奴いないぞ!?
思わずその声のする方へ駆け出してしまう。そうせずにはいられなかった。
その声の主はすぐにわかった。川向こうの夕日に歌いかけるかのように、こちらに背を向けていて、顔はわからなかったが、只者じゃない雰囲気は背中越しでも十二分に伝わってくる。
息を切らして駆け寄ったケンスケに気づいたその声の主は、歌を歌うのをやめ、ゆっくりと振り返る。
「……。」
「あ…ご、ごめんな。つい聞き入っちゃってさ。…歌、うまいんだな。」
「……。」
「その制服。同じ凰学生だよな? 名前、聞いてもいいか?」
「……VALSHE。1年。」
言葉少なに名乗るどこか浮世離れした“そいつ”の姿に、ケンスケは目をそらすことができなくなっていた。
“もしかしたら…”そんな思いがよぎったケンスケは思わず、こう口にしていた。
「…なぁ、俺らのバンド、3年になってすぐに一人抜けちゃってさ。いないんだよ、ボーカルが。」
――最後なんだ。俺らのバンドの、軽音楽部の、最後のライブに協力してくれないか?その声となら、きっと…いいライブができると思うんだ――
その後、凰学生の間で何年もの間、伝説として語りつがれることになる軽音楽部の物語が、静かに動き出した。